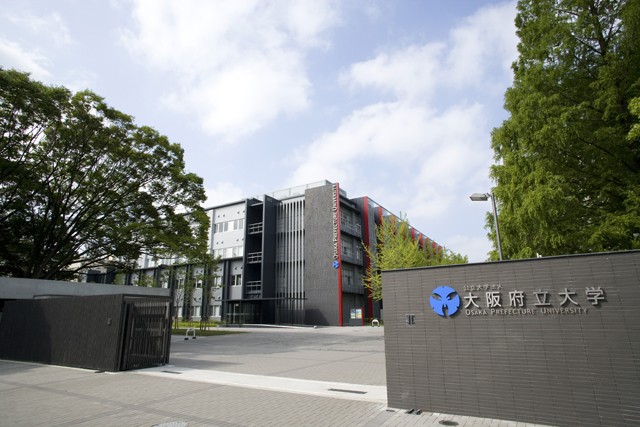2018年1月22日(月)、堺市(〒599-8531堺市中区学園町1番1号)の大阪府立大学C1棟の学術交流会館にて「私たちの健康と食品の三次機能」というテーマ特別講演会が開催されました。しかし、大阪府立大学の広大な敷地には驚かされました。聞くところによると、全国でも有数の広大な敷地を持つ大学のようです。
前段は、生命環境科学研究科の大松さんによる「紫黒米米糠酵素処理物を用いたフェルラ酸のバイオアベイラビリティの向上」、後段が前田博士の特別講演で、テーマは「防衛体力を強化し生命力を高める植物の働き」というもの。先生の講演はある雑誌社の取材も兼ねたものでしたが、対象は大学の研究者の方々。
大松さんの研究発表では、フェルラ酸に、抗酸化作用、不動脈硬化の改善やアルツハイマー予防作用などの多くの生理活性があることが報告されているが、フェルラ酸は水への溶解度が低く、バイオアベイラビリティ(生体内利用率)が低いことが問題となっております。近年オリゴ糖を分散剤として用いることにより機能性化合物の溶解度を向上させ、吸収性の改善を試みる研究が注目されているようですが、大松さんの研究では、紫黒米米糠酵素処理物を用いてフェルラ酸の溶解度を向上させバイオアベイラビリティを高めることを試みておられました。
後段の前田博士の講演。先ずは博士の生い立ち(生家は瀬戸内海の醤油蔵で麹まみれの環境で育たれたようです)に始まり、サプリメントと健康食品の区分解説、千葉大学での蓮の研究、そして博士の研究テーマである防衛体力強化を目的とする栄養素以外での命力を強化する食品成分の素材開発のレビュー(1970年代のシイタケ培養物を加工した製品の研究に始まり、1980年代のAHCC(活性化糖類関連化合物)の開発、1990年代のアラビノキシランの開発、2005年弘前大学との共同研究による「オリザロース」の開発の経緯等々)、統合医療の医師たちとの協力を得た啓蒙活動等々、長年の博士の研究成果の集大成というべきもので、極めて面白くかつ分かり易く、そして博士の素晴らしいお人柄がよくわかる内容のものでした。「開発には、科学的なアプローチだけではだめで、情緒性も大変重要である」、「良い人、良い風土、良い環境がないと良いものは作れない」という博士のお言葉がとても新鮮で今でも忘れらません。
古代米の一種である紫黒米を原料とし、米ぬかの植物繊維の持つ力を引き出し、機能的な糖鎖の構造を残したままで消化吸収できる大きさに低分子化したものを主原料とする「スーパーオリマックス」ですが、長年の研究の積み重ねと博士の直感力と着想力、そして関係者の皆さまの多大なる協力があって初めて出来上がったもので、紛れもない本物であることが良く理解できました。とても貴重な経験をさせて頂き感謝いたします。